建設コンサルタントの仕事
建設コンサルタントの仕事はクライアントへの工事提案からはじまり、契約処理や工事の企画、設計、管理など幅広く担当します。事務作業や営業活動を重ねながら、受注したクライアントとは定期的に打ち合わせを重ね、必要事項を現場関係者へ連携していきます。
現場のゼネコン関係者を管理する役割を担っており、工事進捗や現場との連携は建設コンサルタントの力量によって左右されるといっても過言ではありません。
建設コンサルタントの仕事
建設コンサルタントの資格
「建設コンサルタント」になるためには、必須の資格はありません。就職が有利になる資格として、近地区施工管理技士や土木施工管理技士が挙げられます。とくに土木関連の現場では実務経験が重視される傾向があります。
国家資格である技術士は、二次試験に実務経験があり、専門的な知識と実務経験の両面からアピールできるため、取得を検討しても良いでしょう。
建設コンサルタントの資格
建設コンサルタントになるための学校
直接的に「この学校に行くと建設コンサルタントになれる」という学校はありません。建設コンサルタントとして働くことを見据えるなら、土木関連の専門知識を獲得できる学校へ進むのが良いでしょう。
卒業生に建設コンサルタントがいる学校は就職で有利に働く可能性が高いため、卒業生の就職先一覧などを確認しておくのがおすすめです。
建設コンサルタントになるための学校
建設コンサルタントに向いている人
専門領域を深めていく職種ではなく、あらゆる領域のプロと関りながら、臨機応変な対応が求められるのが建設コンサルタントです。ゆえにマルチタスクで仕事ができたり、隔たりなくコミュニケーションを取れる人が向いているでしょう。
また、細かなスケジュール管理が求められる仕事でもあるため、コツコツとマメに努力を重ねていける人が向いています。
建設コンサルタントに向いている人
建設コンサルタントの年収
年収が平均的に低いとされる建設業界の中で、平均年収は550万程度と比較的高い職種です。年齢と共に収入が上昇していく傾向にあり、500万円を超える収入は40代以上となる場合が多いようです。
年齢の他に地域差があり、地域によっては20代の年収でにとどまる場合もあるようです。お住いの地域の企業の年収などを参考にすると安心です。
建設コンサルタントの年収
建設コンサルタントの就職先
建設コンサルタント会社はもちろん、技術研究所やシンクタンクでも、建設コンサルタントは求められています。企業によって扱う範囲が異なる職種であることを前提に、さまざまな企業を見て「働きたい!」と思う企業を見つけられるのがベストです。
地方と都市部によって働き方が大きく異なるため、希望する働き方を考えたうえで、企業探しを行うと良さそうです。
建設コンサルタントの就職先
建設コンサルタントの将来性
近年、日本国内では世界的な祭典やイベントが数多く開催されているほか、渋谷などを中心に都市部の再開発が進んでいます。そのため、道路や公共施設に多額の設備投資が実施されており、2025年頃までは安泰の職種と言えるでしょう。
日本は元々インフラ整備にかける金額が高くありません。より高収入を目指す場合は海外派遣などを視野にキャリアを積んでおくと将来性としては安心です。
建設コンサルタントの将来性
建設コンサルタントの歴史
イギリスで産業革命が起こった18世紀末に誕生した建設コンサルタントは、世界各国でインフラ整備などを実施する際に重宝されてきました。
日本では1964年に登録制度が整備され、建設省により土木と設計会社を分けることが義務付けられたため、双方の間を取り持つ建設コンサルタントが重宝されるようになりました。次のページでは建設コンサルタントの歴史について分かりやすく解説します。
建設コンサルタントの歴史
大手の建設コンサルタント会社
日本の建設コンサルタント会社のなかで『大手』といえば、「日本工営」や「建設技術研究所」、「オリエンタルコンサルタンツHD」などが挙げられます。具体的な定義が決まっているわけではありませんが、売上高が大きかったり、業界内での知名度が高かったりする企業を大手と呼ぶケースが多いようです。
次のページでは規模が大きい、売上高が大きいなどの条件に当てはまる有名企業を紹介します。
大手の建設コンサルタント会社
転職と年齢の関係
一般的には若いほうが転職に有利とされていますが、建設コンサルタントでは20代の若手はもちろん、即戦力としての活躍が期待できる30代のニーズも高いようです。
逆に今の会社から別の会社へ、もしくは別の業界へ転職したい場合は、20~30代のうちに動いていたほうがスムーズに転職できる可能性が高くなります。とくに未経験の分野にチャレンジしたい場合は、20代のうちに動いておいたほうが良いでしょう。
転職と年齢の関係
キャリアプランの考え方
建設コンサルタントとして自身の専門分野を極め、一人前と認められるようになるには10年ほどかかります。つまり、建設コンサルタントとして働き始めてから10年ほどは、キャリアプランはほぼ1本道です。
経験を積み、名実ともに一人前の建設コンサルタントとして認められるようになると、「そのまま技術者として腕を磨くか」「役職を目指し、マネジメントにかかわるか」「独立して起業するか」といった可能性が広がります。
建設コンサルタントのキャリアプラン
建設コンサルタントの種類
単純に「建設コンサルタント」と言っても、その種類は国土交通省による登録部門によってさまざまです。登録部門の中でもメジャーなのは、土木系の建設コンサルタントや建築系の建設コンサルタントでしょう。また、特定の業務に特化した専門系の建設コンサルタントも存在します。どの部門を選ぶかによって仕事内容や特徴が異なるため、あらかじめ種類ごとの違いを知っておくのが重要です。
建設コンサルタントの種類
建設コンサルタントの志望動機
建設コンサルタントに限らず、就職・転職に成功するためには具体的かつ分かりやすい志望動機が欠かせません。特に建設コンサルタントの仕事においては、「社会貢献」をキーワードに志望動機を考えるのがポイントです。以下のページでは、建設コンサルタントの就職・転職における志望動機の重要性や評価されやすいアピールポイント、履歴書を書く際の注意点などを紹介しています。
建設コンサルタントの志望動機
建設コンサルタントの面接対策
就職活動や転職活動を成功させる上では面接対策が必須。建設コンサルタントはクライアントへの合理的な解決策の提示やプラン提案が求められる職業のため、担当者からの質問には一貫した論理性のある回答をするのが大事です。以下のページで、面接前に必要な準備や一次面接・最終面接で頻出する質問について見てみましょう。
建設コンサルタントの面接対策
建設コンサルタントの配属先
就職する企業にもよりますが、面接時に希望の配属先は確認してもらえるのが一般的。しかし、会社の方針や希望する部署の人員構成も関わってくるため、希望の部署に配属されない可能性もあります。希望部署への思い入れが強いのなら、入社前の配属先の確認が必須です。もし、希望の配属先にならなかった場合でも、やりようによっては有用な時間を過ごせます。
建設コンサルタントの配属先
建設コンサルタントの高齢化
建設コンサルタント業界では高齢化が進んでいます。国土交通省が発表している資料によると、平成27年における建設業就業者の年齢は55歳以上が約34%です。高齢化が進むと、技術の承継をスムーズに行えません。問題を解決するため、働く環境の改善、納期の分散などが進められています。
建設コンサルタントの高齢化
建設コンサルタントの転職エージェント
建設コンサルタント業界への転職を検討している方は、転職エージェントに相談するとよいでしょう。転職エージェントは、建設業界専門のサービスとさまざまな業種を扱っているサービスにわかれます。ここでは代表的なサービスをピックアップして、それぞれの特徴を紹介しています。
建設コンサルタントの転職エージェント
建設コンサルタントと建設会社の違い
建設コンサルタントと建設会社の違いをご存知でしょうか。この2つは業務内容に大きな違いがあります。建設コンサルタントは企画・計画・調査・設計・施工管理が主な業務内容で、発注者の支援を行うのが役割です。それに対し建設会社は建設工事を行うのが主な業務内容。ここでは、さらに細かな違いについて解説します。
建設コンサルタントと建設会社の違い
建設コンサルタントのテレワーク可否
近年は幅広い業界でテレワークが推進されています。建設コンサルタントの仕事もテレワークで対応可能です。テレワークによるメリットは、通勤時間の削減やQOLの向上などさまざまあります。建設コンサルタントも同様に、通勤時間・通勤にかかるストレスを削減可能です。ここでは、建設コンサルタントのテレワーク推進のメリットを解説します。
建設コンサルタントのテレワーク可否
海外で建設コンサルタントとしてはたらくには
海外で建設コンサルタントとして働くには、主に3つの方法があります。日本と同じように海外で建設コンサルタントとして働く方法、発展途上国に出向し現地の業務をサポートする方法、そして海外留学により事業を研究する方法です。ここでは、建設コンサルタントとして海外で働く方法について詳しく解説し、さらに海外での取り組みに関しても紹介しています。
海外で建設コンサルタントとしてはたらくには
建設コンサルタントのワークライフバランス
建設コンサルタント会社は完全週休2日制で残業が少なく、年収が高いという傾向があり、ワークライフバランスの充実度が高いと言われています。最近では政府が打ち出した「働き方改革」の考えに沿って、長時間労働をなくそうとする活動が各企業で行われていることも理由のひとつでしょう。ここでは建設コンサルタント会社のワークライフバランスについてさらに詳しく解説します。
建設コンサルタントのワークライフバランス
建設コンサルタント資格のCPD制度とは?
CPD制度は、建築関連の技術者を対象とする専門的な継続教育の制度です。業務の国際化が進みAPEC Engineerと技術士の相互認証が議論となり、海外の資格と同等性を確保する目的で制度化されました。現在では、総合評価落札方式の評価項目である配置予定技術者でCPD制度の配点が設定されています。ここでは、CPD制度が導入された背景、制度の概要などとあわせてRCCMがCPD単位を取得する方法、CPD単位取得に必要な費用などを解説しています。
建設コンサルタント資格のCPD制度とは?
建設コンサルタントのデジタル化
建設コンサルタント業界が直面する主な課題として、少子高齢化の進展による担い手不足などがあげられます。課題の解決に有効と考えられるのがデジタル技術の活用です。例えば、BIMやCIMを活用して業務の効率化を進めることにより担い手不足に対処できる可能性があります。ここでは、建設コンサルタント業界が直面している主な課題と課題を解決するために各社が行っているデジタル化の取り組みなどを紹介しています。
建設コンサルタントのデジタル化について
建設コンサルタントが使用する業界用語とは
建設コンサルタントとしてスムーズに業務を進めていくためには、日々の業務の中で使われることが多い業界用語について正しく理解しておくことが重要です。建設業界でよく使われているものの、一般的にはなじみのないような言葉も多くあります。おさえておきたい業界用語についてまとめました。また、難しい業界用語をどのようにすれば効率よく覚えられるのかについても紹介します。資料を用意する、都度調べる、メモを取るなどの方法に取り組みましょう。
建設コンサルタントが使用する業界用語について
建設コンサルタントのコンプライアンス
建設コンサルタントを目指すにあたり、どのようなコンプライアンスがあるのかについて確認しておくことをおすすめします。建設コンサルタントは建設業に関する専門家ということもあり、コンプライアンス違反に繋がらないように十分注意が必要です。過去には、コンプライアンス違反が原因で事業停止の措置が取られたようなケースもあります。そこで、おさえておきたい建設コンサルタントのコンプライアンスや、違反の事例について紹介します。
建設コンサルタントのコンプライアンスについて
公務員から建設コンサルタントになる人が増えている?
安定的な職業として人気の高い公務員ですが、近年では業務で得た知識や経験を活かし、建設コンサルタントに転職をするケースがみられます。土木や建築など、公務員の業務内容と建設コンサルタントの業務は似た部分も多く、転職によって専門知識を活かしながら給与や待遇の向上も図ることができます。難しい裁量権のある仕事を任せてもらえるなど、建設コンサルタントには公務員にないメリットがあります。
公務員から建設コンサルタントになる人が増えている?について
建設コンサルタントと経営コンサルタントの違いとは
建設コンサルタントは、公共事業や街づくり、地域の防災計画などに関わり、企画や提案を行いながら社会資本整備に関わる事業を進める仕事です。一方、経営コンサルタントは民間の企業や法人の経営状態や事業の方向性を確認し、問題点を洗い出したうえで顧客が抱えている悩みの解決を目指します。コンサルティングを行う点については共通していますが、専門領域がそれぞれ異なることや、顧客が公共機関か、あるいは民間の事業者かという違いがあります。
建設コンサルタントと経営コンサルタントの違いとはについて
建設コンサルタントの結婚事情
仕事によっては、結婚しづらいと認識されている職業があります。建設コンサルタントは、職場に男性が多いことや、勤務時間が長くなりがちで、出会いの場に足を運ぶことが難しいことなどから、結婚しづらい職業だと感じている人が多いようです。そのため、建設コンサルタントとして働いている人は、結婚をするにはどうすればよいのか考えている人も少なくありません。ここで、建設コンサルタントが結婚しづらい理由について考えてみましょう。
建設コンサルタントの結婚事情について
建設コンサルタントの災害対策
建設コンサルタントの業務は幅広いですが、災害対策や災害発生時の対応を明確にしておくことは、重要な業務のひとつです。災害に関わる仕事にもさまざまなものがあり、ハザードマップを作成するのも建設コンサルタントの仕事のひとつですし、災害対策を検討するために、災害における被害予測を立てることも建設コンサルタントの仕事になります。建設コンサルタントは、建築業界において実に重要な存在であることが理解できますね。
建設コンサルタントの災害対策について
建設コンサルタントの中途採用時の注意点は?
建設コンサルタントは新卒では教育に時間がかかり、30代の採用は難しいことから人材不足の傾向にあり、40代以降の方の中途採用率が高い傾向にあります。しかし中途採用時には注意したいことがあるのも事実です。中途採用で建設コンサルタントとして雇用された場合、注意するべき2つのポイントについて見ていきましょう。
建設コンサルタントの中途採用時の注意点について
建設コンサルタントの出張頻度
建設コンサルタントは出張頻度が高い職業だと言われています。出張が多い仕事への抵抗感を持っている方もいるかもしれませんが、出張にはメリットや楽しみもあります。出張手当がもらえたり、ポイントやマイルを貯められたりするのはメリットと言えるでしょう。ここでは建設コンサルタントが頻繁に出張する理由や、出張を楽しむためのコツとメリットを紹介します。
建設コンサルタントの出張頻度について
建設コンサルタントの転職前に押さえたいビジネスマナー
建設コンサルタントは都市計画や現場の調査など、フィールドワークが多い一方で多くの顧客と接する職業です。普段から会社のイメージを背負って顧客と接することを念頭に置き、社会人らしいビジネスマナーを押さえておくことで好印象を与え、会社のイメージアップを図ることができます。ここでは、建設コンサルタントへの転職前に押さえておきたいビジネスマナーについて紹介します。
建設コンサルタントの転職前に押さえたいビジネスマナーについて
建設コンサルタントとSDGsの関係性とは
建設コンサルタントは、既存の街や建物を次世代に繋ぐための街づくり、さらには災害復興を進めるための街づくり計画に携わることがあり、環境保護や開発国支援などの取り組みも期待されていることから、「SDGs」についての知識・理解が求められています。この記事ではSDGsとはどのような取り組みなのかについて改めて紹介し、建設コンサルタントとSDGsの関わりや実際の例を含めて紹介しています。
建設コンサルタントとSDGsの関係性について
今後の建設コンサルタント業務に必要な3DCADとは
3Dプリンターの普及により、最近では建設コンサルタント業務に3DCADの知識と技術が必要とされるようになりました。しかし初心者の方が、3DCADを操作してスムーズに図面を作成するのは難しいものです。そこでこの記事では、3DCADの基本知識を学ぶための学習法について、3つのポイントを解説します。
今後の建設コンサルタント業務に必要な3DCADについて
建設コンサルタント業界で推進される新3Kとは
これまでの建設業界は「汚い・危険・きつい」の3Kであると言われてきましたが、昨今の建設コンサルタント業界では、人材不足解消と生産性向上を目指すために、「給与が良い・休暇が取れる・希望が持てる」の「新3K」が推奨されています。この記事では新3Kの詳細と、新3K実現に向けての業界における動向について解説します。
建設コンサルタント業界で推進される新3Kについて
技術士の次は中小企業診断士を目指そう
技術士として中小企業診断士の仕事を受けている方がさらに上を目指したいと考えた際、おすすめの資格が中小企業診断士です。中小企業診断士は、おもに企業が抱える経営課題を解決するためのアドバイスなどを行います。中小企業診断士の資格も取得しておくと建設コンサルタントとして対応できることが増えるため、働き方の選択肢も増えるでしょう。この記事では建設コンサルタントの詳細や、技術士とのダブルライセンスがおすすめの理由などを解説します。
技術士の次に目指したい中小企業診断士について
建設コンサルタントが技術提案書を作成するポイント
建設コンサルタントが行う業務の一つが、技術提案書の作成です。技術提案書の出来によって発注してもらえるかどうかが決まります。建設コンサルタントとして技術提案書を作成する際には、相手の立場に立ち、ツボを把握したうえで文章を作成することが欠かせません。わかりやすい文章を作ることも重要です。ここでは技術提案書の作成を依頼された際、何に注意すれば良いのか、どうすれば相手に伝わりやすい文章が書けるようになるのかなどについて解説しています。
建設コンサルタントが技術提案書を作成するポイントについて
建設コンサルタントに求められる英語力
建設コンサルタントとして働くにあたり、必ずしも英語力が求められるわけではありません。ただ、就職先による違いが大きいため、特に海外事業部などで働くような場合、英語が話せることが前提となります。建設コンサルタントとして活躍の場を広げていきたいと考えているのであれば、英語力を高めることについて検討してみると良いでしょう。英語力は必要か、どういった場合に英語力が求められるのかなどについて、おさえておきたいポイントを解説します。
建設コンサルタントに求められる英語力について
建設コンサルタントは文系出身でもなれるのか
建設コンサルタントとして働いている方の多くが理系出身です。ですが、文系出身だからといって、建設コンサルタントになれないとはいいきれません。さまざまなことについて学んでいかなければなりませんが、文系でも積極的に採用している会社もあります。どのような理由から文系出身でも建設コンサルタントになれるといえるのか、建設コンサルタントを目指すにあたり、理系はどういったことをおさえておきたいのかなどについて解説します。
建設コンサルタントは文系出身でもなれるのかについて
建設コンサルタントの一種「ランドスケープコンサルタント」とは
一口に建設コンサルタントといってもさまざまな種類がありますが、その中の一つであるランドスケープコンサルタントとは、主に景観に関する大規模な開発を中心とした業務を行う仕事です。例えば、リゾート開発や公園・緑地開発なども担当することになります。デザイン面だけではなく、地域の安全や環境、福祉、健康など、さまざまなことに配慮しながらコンサルタントを行わなければなりません。ランドスケープコンサルタントの基本や業務内容について解説します。
建設コンサルタントの一種「ランドスケープコンサルタント」について
建設コンサルタントはフリーランスでも働くことが可能?
建設コンサルタントとして働きたいと考えた際、独立してフリーランスを目指したいといった方もいるでしょう。建設コンサルタントは何か特別な資格を必要とする職業ではないため、フリーランスとして業務を受けることも可能です。ただし、個人で業務を行うのではなく、企業から下請けで受注するケースが多いです。フリーランスとしてコンサルタントの仕事を受けることは可能なのか、どのような形で仕事の発注先を探すことになるのかなどについて紹介します。
建設コンサルタントはフリーランスでも働くことが可能なのかについて
建設コンサルタントと測量業の違い
建設コンサルタントは建築物をつくるにあたり、企画、計画、調査、設計、施工管理すべての段階で業務に携わります。一方、測量業が担当することになるのは、これらのうち調査にあたる項目です。測量業は、専用の機械を使い、地図の作成や建物の建築に必要な距離や角度、高さを測る仕事です。建設コンサルタントとはどのような違いがあるのか、具体的にどういった業務内容を担当することになるのか、資格は必要かなどについて紹介します。
建設コンサルタントと測量業の違いについて
建設コンサルタントと地質調査業の違い
建設に関する仕事はいろいろあります。例えば、測量業です。測量業は建設全般に対応する建設コンサルタントとは違い、調査の段階を担当する職業です。企画、計画のあとに測量業が地図の作成や建物の建築に必要な距離や角度、高さなどを調査し、設計、施工管理と進んでいきます。測量業の主な業務内容は、建設・土木工事の現場で行う外業と、デスクワークにあたる内業です。建設コンサルタントとの違いや特徴、業務内容、必要な資格などを紹介します。
建設コンサルタントと地質調査業の違いについて
社会資本整備の課題
社会資本整備とは、人々が安全に生活を送り、経済活動の基盤となる道路や橋、ダム、港湾、空港、鉄道、上下水道などの公共インフラを構築、維持する活動のことです。高速道路の整備による物流の円滑化、災害防止施設の設置などが例として挙げられます。基本的には国民のニーズやプロジェクトの必要性を考慮し、国や自治体と業者が計画や施工を進めていく流れとなりますが、建設コンサルタントがプロジェクトをサポートする場合もあります。
社会資本整備の課題について
建設コンサルタントと関係の深い設計・施工分離の原則とは?
建設コンサルタントが誕生したのは昭和30年代頃だといわれています。その頃、社会資本整備の業務量が急速に増えていったことで、インフラの整備が国や自治体だけで対応できなくなり、民間の事業者に依頼するようになったのが始まりです。また、1959年には設計・施工の分離原則が制定され、インフラ整備の設計を建設コンサルタントが担当することになりました。こうした背景があり、現在は設計施工分離発注方式を採用しながら、国や自治体、建設コンサルタントが協力してインフラ整備に努めています。
建設コンサルタントと関係の深い設計・施工分離の原則について
建設コンサルタントが施工監理を経験するメリットとは
建設コンサルタントが施工監理を経験するメリットは、主に3つ考えられます。まず、図面についての理解が深まり、設計に関する知識と理解が深まります。また、依頼主の業務が把握できることで、広い視野でサポートができるようになるでしょう。また、依頼主の状況と現場の流れを知ることも、大きなメリットといえます。施工監理を通じて特定の地域に一定期間滞在することになれば、その土地に適した提案や管理業務を行うことも可能になります。
建設コンサルタントが施工監理を経験するメリットについて
建設コンサルタントの登録制度とは
建設コンサルタントの仕事は、資格や認可が必要ありません。そのため、誰でも建設コンサルタントを名乗り受注することが可能です。そこで、建設コンサルタント登録を行うことで、ほかの業者より優位に立つことができます。建設コンサルタント登録とは、国土交通省が提供する登録制度のことで、一定の条件と必要書類を満たすことで登録が可能です。また、建設コンサルタント登録することで得られるメリットは大きいといえます。
建設コンサルタントの登録制度について
建設コンサルタントの離職率は高いのか
「建設コンサルタントの職業は離職率が高そう」「建設コンサルタントは激務で続かなさそう」といったイメージが定着しているかもしれませんが、ほかの業種と比べ建設コンサルタントは安定した職業だといえます。厚生労働省が調査した結果によると、建設コンサルタントが該当する技術サービス業の離職率は、ほかの業種と比較して低く、建設業界全体の離職率は入職率を下回っています。そのため、比較的安定した職業だと考えてよいでしょう。
建設コンサルタントの離職率について
建設コンサルタントの入札契約方式とは
建設コンサルタントは、公共工事や都市計画、インフラ整備をメインに携わるため、発注者は入札契約方式を採用します。入札契約方式とは、業者がもつ技術力や工事内容、価格などを踏まえ、発注者が求める基準を満たした業者を落札する方式です。現在は主に「プロポーザル方式」「総合評価落札方式」「価格競争方式」の3種類が採用されており、それぞれ選定方法が異なります。また、入札の流れについても解説しています。
建設コンサルタントの入札契約方式について
建設コンサルタントは人手不足か?
近年建設コンサルタント業界は人手不足が問題となっています。経験者の高齢化に伴う退職、専門的な教育の不足、労働人口の減少、業務範囲の拡大などが要因として挙げられます。建設業界全体の人手不足解消として、女性社員の活用、福利厚生の充実、業務量の適正化、働き方改革の推進が必要でしょう。特に健全な労働環境の構築や効率的なオンラインツールの利用は、人材確保とその定着につながると考えられます。
建設コンサルタントは人手不足か?について
建設コンサルタントの現況報告書とは
建設コンサルタントは、登録後も定期的に「現況報告書」などの書類を提出する必要があります。これらの書類は、事業年度終了から4か月以内に提出しなければならず、法人や個人でも提出内容が異なります。現況報告書には、直近の契約内容や業務経歴、財務状況などが詳細に記載されます。特に各書類の金額やデータが一致しているかの確認が重要です。また、株式譲渡制限会社など、会社の種類によって記載内容が変わる点も注意が必要です。正確な書類の提出を怠ると、登録取り消しのリスクがあるため、十分注意しましょう。
建設コンサルタントの現況報告書について
建設コンサルタントと設計事務所の仕事の違いとは?
建設コンサルタントは、設計事務所のように一般住宅や商業店舗を設計するわけではなく、社会資本である道路や河川の整備計画に携わります。計画の段階から発注者である地方自治体などと、施工者である建設会社の間に入り、調整やコンサルティングを行います。かつて大規模災害が発生した地域では、復興や次の災害に備えるといった課題をクリアするために、詳しく現地調査を行って解決方法を考えながら、スムーズな施工に繋げていきます。
建設コンサルタントと設計事務所の仕事の違いについて
建設コンサルタントの講習会とは
建設コンサルタントの講習会は、建設コンサルタントを対象に業務効率の改善や工事の品質確保に役立てられる内容を紹介したり、実際に起きたエラーの紹介によって予防意識の啓蒙を行ったりするものです。近年登場した新たなツールやデバイスの活用、「見える化」やデータの活用といったさまざまな知識が取り上げられるほか、オンライン受講が可能な講義も提供されています。地方では大規模災害や防災をテーマとした講習会も開かれています。
建設コンサルタント講習会について
建設コンサルタントの営業について
建設コンサルタントの営業では、ヒアリング力・提案力・コミュニケーション能力が求められます。また顧客にアドバイスをする立場であることから労働時間外の学習が必要であり、労働時間の長さも相まって、ホワイトな企業の建設コンサルタントでも「激務」とされることがあります。1人で仕事ができるようになるまで、10年ほどかかることも珍しくありません。建設コンサルタントを目指すなら、営業をするために必要な能力や業務の内容についてあらかじめ知っておく必要があります。
建設コンサルタントの営業について
建設コンサルタントとAI技術について
建設コンサルタントがAI技術を活用することにはさまざまなメリットがあります。まず生産性が向上すること、そして建設業界における人材不足を補えることです。AI技術により人力が不要である部分が増えれば、人員が少なくてもより質の高い業務が行えるようになります。実際にすでにAI技術を活用している建設コンサルタントもあり、インフラ管理の高度化やコストダウンなどの成果を実感している顧客も少なくありません。
建設コンサルタントとAI技術について
技術士の資格が役に立たないとされる理由
建設コンサルタントを目指す方の中には、技術士の資格を取っておいたほうがいいのか、迷っている方もいるのではないでしょうか。ただ、技術士の資格は「持っていてもあまり意味がない」と言われることがあります。それは本当なのか、技術士の仕事内容や資格取得に要する期間、取得後のメリットなどから理由をひも解いていきます。受験資格や試験内容といった資格に関する情報についても記載していますので、ぜひ検討の参考にしてみてください。
技術士の資格が役に立たないとされる理由
仕事に関わるインフラプロジェクトとは
インフラプロジェクトとは、国内のインフラを支えることを目的に、既存のサービスや設備を必要に通じて改修や保守をしたり、あるいは新たに設備を建設したりするための計画案のことです。扱う対象によって「ハードインフラ」「ソフトインフラ」の2種類に分けられます。物理的にシステムや設備の保守などをおこなう場合は、主に前者に分類されます。
仕事に関わるインフラプロジェクトとは
プロジェクトに必須となるスケジューリング
より効率的に、そして円滑にプロジェクトを進めていくためには、スケジューリングが重要になります。複数の作業を複数のスタッフで協力して進めていく必要があるプロジェクトを扱う場合は特に、個々の進捗状況をシェアして、柔軟に対応できる環境を整えておくことが求められます。管理ツールを使うと、そういった管理を容易におこなえます。
プロジェクトに必須となるスケジューリング
建築業に必要な構造力学
構造力学は、建築物にかかる荷重や外力の影響を解析し、安全性を確保するための重要な学問です。地震、風、雪などの自然災害に対する建物の強度を計算し、設計に反映させます。これにより、建物の変形や破損を防ぎ、住民の安全を守ることができます。建築業ではこの知識を駆使して、建物の耐久性を高めることが求められています。
建築業に必要な構造力学
建築に関わる材料工学
材料工学は、天然資源を加工して高性能な材料を開発する学問です。金属材料、無機材料、有機材料の特性を研究し、新たな材料の創出や応用技術を追求します。例えば、鉄鉱石を加工して強度の高い鋼板を作り出す技術も材料工学が関わっています。この分野は建築物の安全性や機能性を向上させるために不可欠です。建築コンサルタントにとっても重要な知識となるでしょう。
建築に関わる材料工学




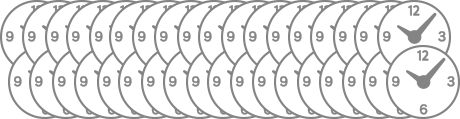
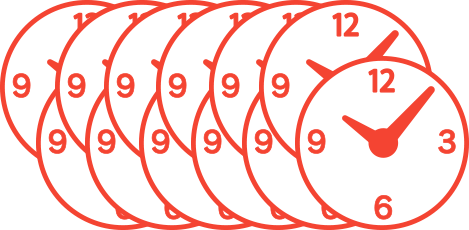
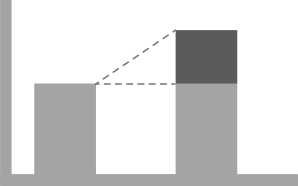












 Sさん(45歳)
Sさん(45歳)